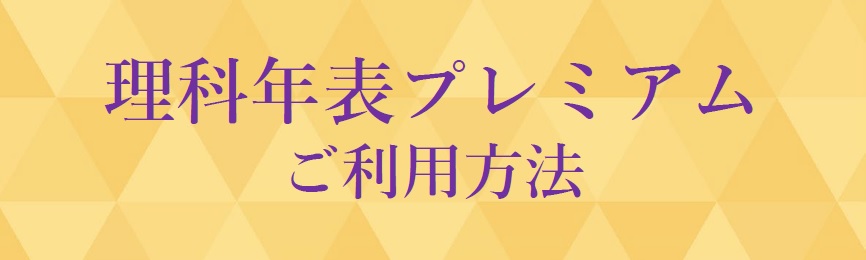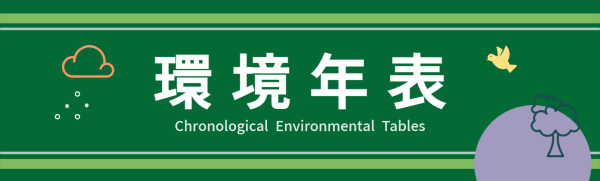有機物と無機物の違いは?
19 世紀中ごろまで地球上にもともと存在する化合物、あるいは実験室で合成できるものを無機化合物、生命活動から生じたものを有機化合物と呼び、有機化合物は実験室では合成できないと信じられていました (生気論と言います )。ところが尿に含まれる尿素がドイツ人科学者ウェーラーによって実験室で合成できることがわかり、さらに弟子のコルベが酢酸 (酢の主成分;酢は穀物を酵母により醸造してできます )を合成し、生気論は衰退しました。現在は炭素原子を基本骨格とする化合物を有機化合物、それ以外のものを無機化合物と分類するようになりました。ただ、慣例として炭素の同素体、ダイヤモンド、グラファイト、あるいは二酸化炭素、一酸化炭素、炭酸ナトリウムなどの金属炭酸塩、青酸 (HCN)と金属青酸塩、シアン酸(H-O-C≡N )、金属シアン酸塩、チオシアン酸(HSCN )、金属チオシアン酸塩は無機化合物に分類されています。その理由は前述したように「有機化合物は生体が産生する化学物質である」とした歴史的な定義が存在したために、ここで挙げた炭素化合物はその当時から生体が関与しない化合物として発見されていたためです。
さて有機化合物は炭素骨格が鎖状のものと環状のものがあります。前者の長さおよび分岐の多様性に関して制限が無く、後者も無限に連結可能で、鎖状ものと環状のものの連結も可能です。そのため複雑な構造を取ることができます。また炭素に窒素、酸素、硫黄、燐あるいはハロゲンなどが結合して生成する官能基も多様で、それぞれが独特の特性を持つことから、炭素骨格の多様性とあいまってほとんど無限といって差し支えの無い多様性を発現します。その多様性ゆえ有機化合物は生物を構成する要素になり、昔の人々が、有機化合物は生物が生み出すものと信じたのも無理からぬことです。一方炭素以外の元素は現在認められているだけでも 100 種類以上あります。ですから、無機化合物も元素の組み合わせにより無限と言っていいほどの種類の化合物が存在します。無機化合物の化学的性質は、元素の価電子 (最外殻電子)の数に応じて性質が多彩に変化します。特に典型元素は周期表の族番号と周期にそれぞれ特有の性質の関連が知られています。遷移元素の場合は、d 電子数の変化に伴い、固有の性質を持ちますが、単純に周期表の族から簡単に性質を予測することが難しくなり、元素ごとに多彩な性格を発揮することが知られています。金属元素の化合物には、水素化合物、酸化物、オキソ酸、水酸化物、ハロゲン化物、硫酸塩、硝酸塩、炭酸塩、酢酸塩、金属錯体 (配位化合物)などがあります。
最近有機分子の炭素骨格に金属元素を導入して、従来にない化合物を合成する試みや、タンパク質に含まれる微量金属の役割の研究が盛んに行われています。また以前より金属と炭素との化学結合を含む有機金属化合物が知られており、その触媒作用が注目されています。先端の科学では、今までの無機化学、有機化学の垣根を越えた研究が盛んになっています。
【梅澤香代子 日本大学文理学部(2008年 5月)】