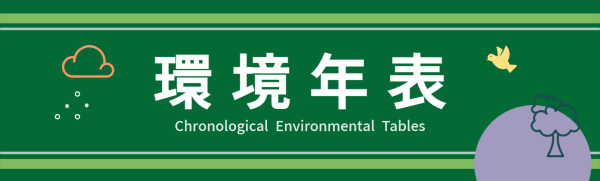気象部「降水量の月別平年値」をくわしく解説!
大気中の水蒸気が凝結または昇華してできた水滴や氷片が地表面や海面に落下する現象、または落下したものを降水という。水滴や氷片は通常雲の中でつくられるが、晴れた日に空気中の水蒸気が寒さのため結晶となって落下する現象である細氷 (ダイヤモンドダスト)も、降水の一種である。
液体の水として降る場合を雨または降雨と呼び、雪、あられ、ひょうなど氷として降るものを固形降水と呼んで、区別することもある。また、雪が半分融けたものをみぞれという。地上では雨として降る場合でも上空では雪やあられであることが珍しくない。
乱層雲(Ns)など層状の雲から降り、雨滴が比較的小さく、また降雨強度の変化が緩やかな降水を一様性 (または連続性)の降水、積乱雲(Cb)など対流性の雲から降り、大粒で、降雨強度が急に変化するものを驟 (しゅう)雨性降水(にわか雨 ・ にわか雪 )という。いわゆる「夕立」は、典型的なしゅう雨性降水である。
霧は降水ではないが、微水滴の落下が目視で確認できる場合すなわち霧雨は降水である。
気象庁が観測を行っている降水に関する観測要素としては、降水量、積雪の深さ、降雪の深さがある。また天気や大気現象に関連して、降水の有無 (観測者の目視や感雨器などによる)や降水強度を観測している。 1 滴の雨または 1 片の雪が観測されれば、「降水あり」となる。ラジオの気象通報で「天気、雨強し」というのは、降水強度が 15.0 mm/h 以上のときをいう。
降水量は、ある時間内に地表の水平面に達した降水の深さ (単位は mm)で表わす。雪などの固形降水の場合は融けたものとする。ただし、露、霜、しぶき、地ふぶきなどによる水と降水とが区別できない場合は、その量を降水量に含める。
内径 20 cm の雨量計で受水し、溜まった水の体積を計測して深さに換算する。かつては貯水型雨量計を用い 0.1 mm 単位で手動計測していたが、 1968 年 1 月からは降水量 0.5 mm ごとにますがシーソーのように転倒する転倒ます型雨量計を用いて自動計測している。
ある期間中に降水があったがその量が 0.5 mm (転倒ます型雨量計の場合)に達しないときは「 0.0 mm 」とし、「降水なし」の場合の「-」と区別 する。
固形降水の場合は、液体の雨のように簡単ではない。固形降水の密度は水より小さく、その値が一定していないので、質量 (重さ)を測るか、一度液体にしてその体積を測る必要がある。現在、気象庁ではヒーターを組み込み、雪などを融かしながら計測する温水式または溢水式の転倒ます型雨量計を使用している。雪質にもよるが、雨量計が熱源を持っていると、対流が生じたり受水口内に落ちた雪が蒸発したりして捕捉率が低下することがある。
降水量の統計としては日 ・ 月 ・ 年などの期間合計値を求める。累年統計や平年値の場合は、期間合計値の平均値を求める。そのほか 10 分間 ・ 1 時間降水量の日最大値も求めており、それらを用いた統計値も算出している。近年、極端に多い降水量と(異常多雨)と極端に少ない降水量( 異常少雨 )が現れやすいことがいわれている。降水量の統計例として日降水量 200 mm 以上の日数の経年変化を図に示す。 20 世紀初頭から観測データの均質性が継続している 51 地点について求めた。
【山内豊太郎(2006年11月)】
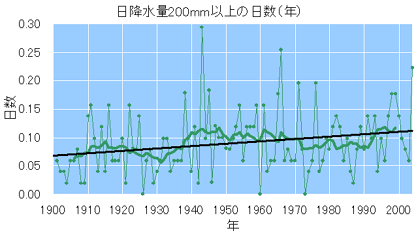
図 日降水量 200 mm 以上の日数
(『 異常気象レポート 2005 』(気象庁) より )
【 参考文献 】
竹内均監修 :『地球環境調査計測事典 第 1 巻 陸域編 ( 1 ) 』、p.16 ~ 18、フジ ・ テクノシステム( 2002 )
気象庁編 :『地上気象観測指針 』、p.52 ~ 56、気象庁(2002 )
気象庁編 :『異常気象レポート 2005 』、p.60 ~ 61、気象庁(2005 )