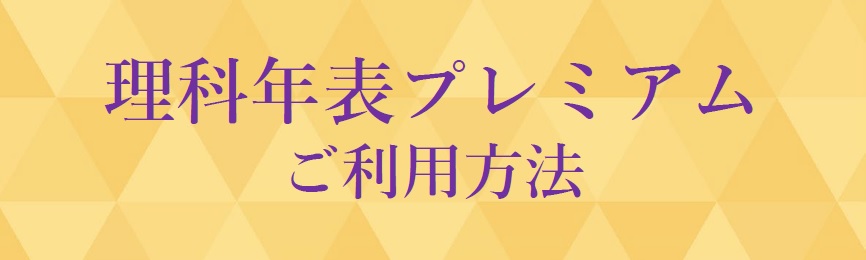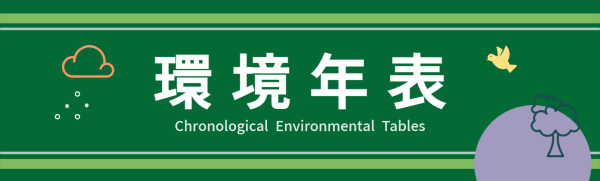気象部「台風」をくわしく解説!
熱帯低気圧は低緯度で発生し、その水平規模は数百 ~ 1000 km 程度、寿命は 1 週間程度である。台風とは、北西太平洋と南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速がおよそ 17 m/s(34 ノット )以上のものと定義される。北東太平洋や大西洋ではハリケーン、インド洋ではサイクロンと呼ばれる。
熱帯海洋上では、太陽エネルギーが海面を温め大量の水蒸気を発生させ、積乱雲が発生しやすい状態になっている。この積乱雲がまとまりをもった大規模な集団として組織化されることにより、熱帯低気圧が発生する。このため、熱帯低気圧は、海面水温が 26 ~ 27 ℃ 以上で、かつ下層の大規模な気流が集まる地域でよく発生する。北西太平洋にはこれらの条件が整っており、熱帯低気圧の発生頻度が高い。
台風は強風や大雨を伴い、洪水、高潮などさまざまな災害をもたらす。気象観測が始まった明治以降に日本に襲来した台風のうち、 1934 年 9 月の室戸台風、 1945 年 9 月の枕崎台風、 1959 年 9 月の伊勢湾台風は、3000 人以上の死者・行方不明者を出した記録的なものであった。近年はダム、堤防、早期避難など災害対策が進み台風による死者・行方不明者は減ったが、「リンゴ台風」の俗称で知られる 1991 年 9 月の台風第 19 号は、4000 億円以上の農作物被害や、5000 億円以上の損害保険金の支払いを記録した。
気象庁では毎年 1 月 1 日以後、最も早く発生した台風を第 1 号とし、以後台風の発生順に番号を付けている。一度発生した台風が衰えて「熱帯低気圧」になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付ける。
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていたが、台風防災に関する政府間組織である台風委員会 (日本ほか 14 ヵ国等が加盟)は 2000 年から、台風には北西太平洋または南シナ海周辺域で用いられている固有の名前 (加盟国などが提案した名前)をつけることになった。 2000 年の台風第 1 号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」の名前が付けられ、以後、発生順にあらかじめ用意された 140 個の名前を順番に用いて、その後再び「ダムレイ」に戻る。台風の年間発生数の平年値は 26.7 個なので、おおむね 5 年間で台風の名前が一巡し、 2005 年の台風第 18 号が再度「ダムレイ」となった。名前は繰り返して使用されるが、大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがある。また、強い熱帯低気圧が東経 180 度より東の領域から北西太平洋の領域に移動して台風になった 2006 年台風第 12 号の場合には、東経 180 度以東の熱帯低気圧監視を担当する米国によってすでにつけられた名前「イオケ」を継続して使用した。この場合のように、登録された 140 個に記されない名前がつけられる台風もある。
[ 表 : 台風委員会がつける台風の呼び名 ]
【山内豊太郎(2006年11月)】
【 参考文献 】
日本気象学会編 :『新教養の気象学 』、p.80 ~ 83、朝倉書店(1998 )
和達清夫監修 :『最新 気象の事典 』、東京堂出版(1993 )