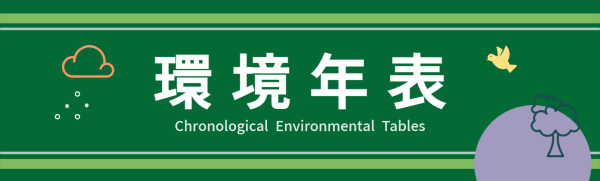環境部「温室効果ガス」をくわしく解説!
地球は大気という蒲団に覆われている。蒲団の内側の温度すなわち地球の地面付近の平均気温は 15 ℃(288 K)だが、蒲団外側の表面温度すなわち放射平衡温度(太陽からの入射量につり合うような地球の黒体放射温度 )は -18 ℃(255 K)である。 288 K の地面が出す放射量と比較すると、 255 K の地球から宇宙に出ている放射量は、約 61 % に相当する。すなわち地表面から出た放射の 39 % は、宇宙空間に出ていないことになる。実際には地面から射出された放射が直接宇宙空間に出て行くのは、赤外線をほとんど吸収しない、いわゆる窓領域と呼ばれるごく一部の波長だけで、大部分の波長の放射はいったん水蒸気・オゾン・二酸化炭素などの吸収気体によって吸収される。吸収気体はその温度に応じた量の放射を再度射出する。このような過程を繰り返した結果、最終的に宇宙から地球を見ると 255 K の黒体に見える。
一方地球に入射する太陽放射は、その 30 % がレイリー散乱や地表面および雲の反射として宇宙空間に戻って行く(理科年表天文部「アルベド」参照 )。残りの太陽光は、紫外線がオゾンに、近赤外域の一部が水蒸気や二酸化炭素に吸収されるものの、大部分は吸収されないで、地表に到達する。
このように大ざっぱにみると、短波長すなわち太陽放射に関しては透明、長波長すなわち地球放射については不透明であるといえる (図 )。そのため、エネルギーは大気を通して地表に入りやすいが、逆に地表から大気を通して出て行きにくいことになり、結果として地表に熱が溜る。これはちょうどガラス屋根の温室が取り込んだ熱を逃がさないので、中の温度が常に外気温より暖かくなっているのとよく似ており、温室効果と呼ばれる。
長波長領域におもな吸収域を持っているのは、二酸化炭素 ・ 水蒸気など大気中の含有量が比較的少ない気体である。以前は温室効果といえばほとんど二酸化炭素だけを考えていたが、このほかにもメタン ・ 一酸化二窒素 ・ 四塩化炭素 ・ メチルクロロフォルム ・ オゾンおよびオゾン破壊で話題のフロン(正式にはクロロフルオロカーボン )・ ハロンなども温室効果を持つことがわかり、現在ではこれらの気体を合わせて温室効果ガスと呼ぶ。これらの中で現在注目されているのは二酸化炭素、メタンおよび一酸化二窒素である。 2000 年現在の大気中の濃度は、二酸化炭素が約 368 ppm で圧倒的に多く、メタンは 1750 ppb で二酸化炭素の 200 分の 1 以下、一酸化二窒素は 316 ppb で 1000 分の 1 以下に過ぎない。その少ないメタンや一酸化二窒素が問題になっているのは、それらの温室効果の効率が高いことと、増加率が大きいことによる。同じ濃度の気体が、ある一定の期間中に二酸化炭素に比べて何倍の温室効果を持つかを地球温暖化指数(GWP)というが、 100 年間で考えると、メタンは GWP が 23 、一酸化二窒素は 296 もある。また、 1750 年を基準にすると、 2000 年までの二酸化炭素増加率は 31 % だが、メタンは 151 % にもなる(一酸化二窒素は 17 % )。なお、フロンは GWP が約 4000 もあって、温室効果気体としても問題になっていたが、一時期約 5 % もあった年間増加率が現在はほぼ止まったので、最近はあまり取り上げられなくなった。しかしその代替物質も温室効果気体であり、その濃度が増加しているので、注意が必要である。水蒸気については、温室効果は大きいが、供給源が自然界にほぼ無限に存在することと、大気中の含有量が飽和水蒸気量以上にはならないことから、他の気体とは区別して考えることが多い。
【山内豊太郎(2006年11月)】

図 地球温暖化の概念図
(『 異常気象レポート 2005 』(気象庁)より )
【 参考文献 】
嶋村克 ・ 山内豊太郎 :『天気の不思議がわかる本 』、p.51、廣済堂(2002 )
気象庁編 :『異常気象レポート 2005 』、p.163 ~ 164、気象庁(2005 )