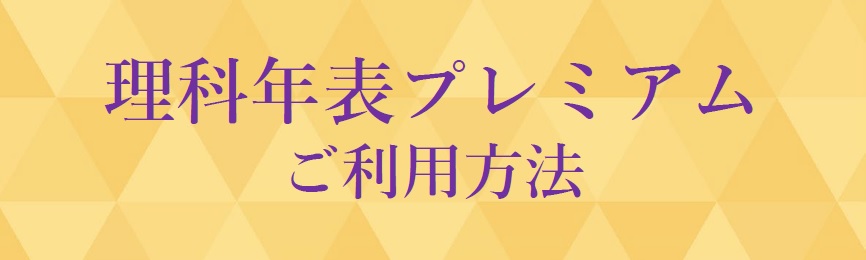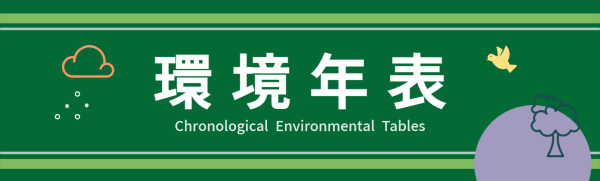気象部「日降水量・1時間降水量・10分間降水量の最大記録」をくわしく解説!
「降水量の月別平年値」の項で述べたように、降水量はある時間内に地表の水平面に達した降水の深さ(単位は mm)で表わす。滝のような雨が短時間降る場合と、並の強さの雨が何日も降り続く場合では、注意すべき災害も異なる。したがって気象庁では期間として、日 ・ 月 ・ 年などの期間合計値のほか、 10 分間 ・ 1 時間降水量の日最大値も求めて統計値を算出している。
一般に、 1 時間当たりに換算した降雨強度は、短時間の記録ほど大きい。
日降水量とは 1 日に降った降水量であるが、かつて観測者が露場の貯水型雨量計で手動観測をしていたときには、 24 時 ( 午前 0 時 ) が各観測地共通の観測時刻ではなかったので、 1 日の境界 ( 日界と呼ぶ ) が 22 時や 09 時などであった。転倒ます型雨量計を用いて自動計測ができるようになってからは、日降水量を 24 時日界で観測するようになった。
1 時間降水量および 10 分間降水量は、 1 分刻みの観測値から連続する 1 時間および 10 分間の降水量を計算し 1 日の最大値を求めている。
大気が含むことのできる水蒸気量 (絶対湿度)は気温が高いほど大きいので、一般的には温暖な地域ほど多雨であるといえる。また大雨は台風のときや前線が停滞しているときなどに降ることが多いが、そのようなときには南からの湿った南東風が山にぶつかって起こることが多い。そのため南東に向かっている斜面、具体的には宮崎県、高知県西部、徳島県、和歌山 ・ 奈良 ・ 三重県、静岡県などでよく大雨が降る。さらに梅雨末期の停滞前線上に次々と発達した積乱雲が発生し、いわゆる集中豪雨をもたらすことがあり、長崎県や山陰地方でしばしば起こっている。
気象台や測候所における降水量の最大記録としては、理科年表の当表題の項に出ているように日降水量は尾鷲の 806.0 mm、 1 時間降水量は清水(高知 )の 150.0 mm、 10 分間降水量は清水の 49.0 mm であるが、気象庁以外の官庁、地方公共団体、電力会社などの記録では、日降水量は海川(徳島)の 1317 mm、 1 時間降水量は長与 (長崎)の 187 mm がある(気象年鑑、 2007 )。
そのほかの期間としては、大雨に関する注意報や警報を出すときに 3 時間降水量を参考にすることも多い。地域によって基準が異なるが、 3 時間降水量が 30、 60、 100 mm などに達すると、それぞれの状況に合わせて大雨による災害に注意する必要がある。ちなみに 3 時間降水量の記録としては、気象台や測候所では仙台空港の 338 mm、アメダスでは多良間(沖縄)の 383 mm がある。
降水量の月別平年値の項で触れたように、近年大雨の日数が増加している傾向がある。
【山内豊太郎(2008年 3月)】
【 参考文献 】
『気象年鑑 2007 年版』、気象業務支援センター